ARCHIVE#01 「八咫烏チーム」の壮大な実験
(この記事は2022年当時の内容です)
日本神話に登場する三本足の八咫烏(やたがらす)。阿部智里著「八咫烏シリーズ」は、人間の姿に変身できる彼らの一族が、異世界・山内(やまうち)を縦横無尽に飛びまわる和風ファンタジー小説です。日嗣の御子・若宮や側仕えの少年・雪哉ら、魅力的なキャラクターたちや、日本神話に通じる壮大な世界観が話題を呼び、150万部を超える大ヒットシリーズに。が、そこにいたる道のりは決して一直線ではありませんでした。作品の誕生から、多くの読者に届けるまで、各部署による“実験”があったのです。八咫烏チームを代表して7人が語ります。(部署は取材当時)



2008年4月、母校の前橋女子高校の講演会に呼ばれ、仕事について話した時のこと。終了後、校長室にひとりの少女が飛び込んできました。高校2年生になったばかりの彼女は「将来、小説家になりたいんです」と熱く語り続け、とうとう下校のチャイムが……。近所で夕食をとりながら話を聞くうち、きらきらした目で見せてくれたガラケーの画像フォルダの中には、下鴨神社で入手した資料や日本古代の神々の系図がビッシリ。「この16歳は只者ではないかも……」。資料への探求心、溢れる想像力と熱量は、往年の歴史小説・社会推理小説の大家、松本清張を彷彿とさせました。
「本気でプロになりたいなら、松本清張賞に応募してみては」。そこから、少女の怒濤の執筆が始まりました。時折、携帯に電話すると「今、塾に行くので自転車に乗ってるんです」ということも。勉強の合間に恐るべき気迫で書き上げた作品でしたが、最終候補作を決める社内選考で、激論の末、惜しくも落選――。
この少女こそが、阿部智里さんであり、応募作のタイトルは『玉依姫』でした。そう、シリーズ5巻目の原型がこの時すでにあったのです。
阿部さんは、ベテラン文藝編集者の「なぜ焦るの? 才能のある人はどんなことがあっても作家になるし、我々はいつも新しい才能を探しているよ」という言葉に励まされ、翌年は受験勉強に専念。早稲田大学文化構想学部で歴史や神話を学びつつ、執筆をつづけることになります。
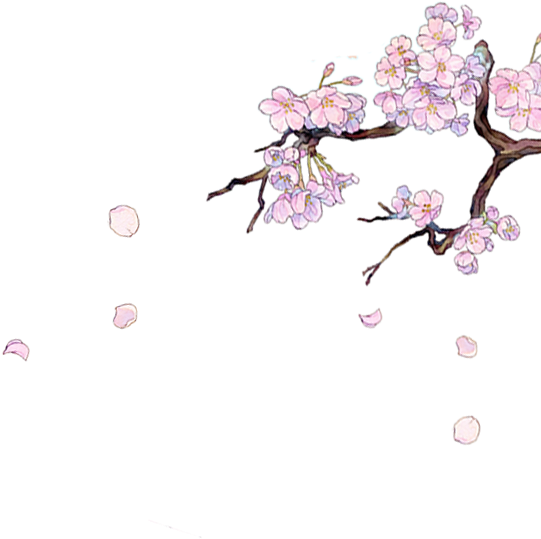


2012年、阿部さんはついに史上最年少で松本清張賞を受賞。『烏に単は似合わない』は20歳の女子大生のデビュー作と話題になりました。でも実は、シリーズは3巻で打ち切りの可能性もあったのです。新人賞を受賞しても、人気作家になるのはそう簡単ではありません。
ところが阿部さんには先々までの構想があり、「小説の舞台で起きることはすべて決まってるんです。私はどこにフォーカスを当て、どう編集して書くか、映画監督のような役割です」と、熱く語られます。
では編集者の役割とは? まずはコーチ役として、作品のブラッシュアップを目指し、年に1冊刊行という締切をクリアすべく叱咤激励します。合言葉は「今日は出前とりますか?」。大学院生としての多忙な日常から引き離し、弊社ビルの中にある執筆室(机とベッドだけの小部屋です)に泊まりこみで執筆=いわゆる「缶詰」にするのが恒例行事となりました。私は「アメとムチ」では後者を選びがちなタイプですが(笑)、あまりに執筆室への出前が続くので、栄養補給食品や、手製ゴーヤチャンプルーまでさしいれ。八咫烏シリーズには「アメもムチも」で伴走しました。
作品ができたら、その面白さをストレートに伝えるために、カバーの装画や帯のコピーをどうすればよいか。著者やデザイナー、営業部や宣伝プロモーション局と相談しながら決めていくのも、編集者の仕事です。その結果、3巻は、長くて覚えにくいといわれたタイトルを『黄金(きん)の烏』に変更。同時期に発売される文庫1巻目のカバーは、単行本とがらりと雰囲気を変え、あえてキャラクターの顔を見せない後ろ姿にして、背景である和風ファンタジーの世界観を前面に打ち出しました。
思い切った試みでしたが、文庫は発売翌日に大増刷。ここから150万部への快進撃がはじまったのです。



書店にたくさん並ぶ新刊本のなかで、大事なのは、平積みで目立つ場所に置いてもらうことです。どんなにデザインや帯に趣向を凝らしても、読み手の眼に入らなければ意味がないからです。ましてや「八咫烏」はシリーズです。新刊が出たとき、旧刊や文庫も並べて売ってもらいたい! でも書店のスペースは限られていて、そう簡単ではありません。
そこで大切なのは、書店員さんに八咫烏のファンになってもらうこと。スポーツでも音楽でもアイドルでも、ファンの力ってすごいですよね。それは本の世界も同じです。書店員さんがファンになってくれれば、シリーズ全巻を並べていただけて、百人力です!
この方針に著者も全面的に協力してくださり、これまでの新刊発売時はサインをしに全国の書店を訪問。サイン本が1日に1000冊近くなることもありました。阿部さんは、書店員さん一人ひとりの目をみつめて、「よろしくお願いします!がんばって面白い作品を書きますので!」と明るく謙虚に挨拶されるので、誰もがファンになってしまいます。地域の書店員さんに集まっていただき「著者と飲み会」を開催したことも(阿部さんはお酒を飲まれませんが)。残念ながら、2020年の新刊『楽園の烏』刊行時はコロナ禍で書店を訪問できませんでしたが、代わりに開催した「著者とZoom懇親会」では、さらに多くの全国の書店員さんと語り合っていただきました!
手作り感も、ファンの熱気を伝えるには大切です。初の文庫化のときは、阿部さんと同世代の女性の営業部員が、4人の姫君それぞれのイラストで手描きPOPをつくりました。恒例となった「店頭装飾コンクール」では、全国の書店さんが、手作りのイラストやボードで八咫烏の世界を表現しています。Twitter「#八咫烏シリーズ応援団」で検索して、その熱気をぜひチェックしてみてください。
リアルな書店の店頭でも、SNSでも、あらゆる知恵と手段を尽くしてファンを獲得していく、それが営業部の仕事です。
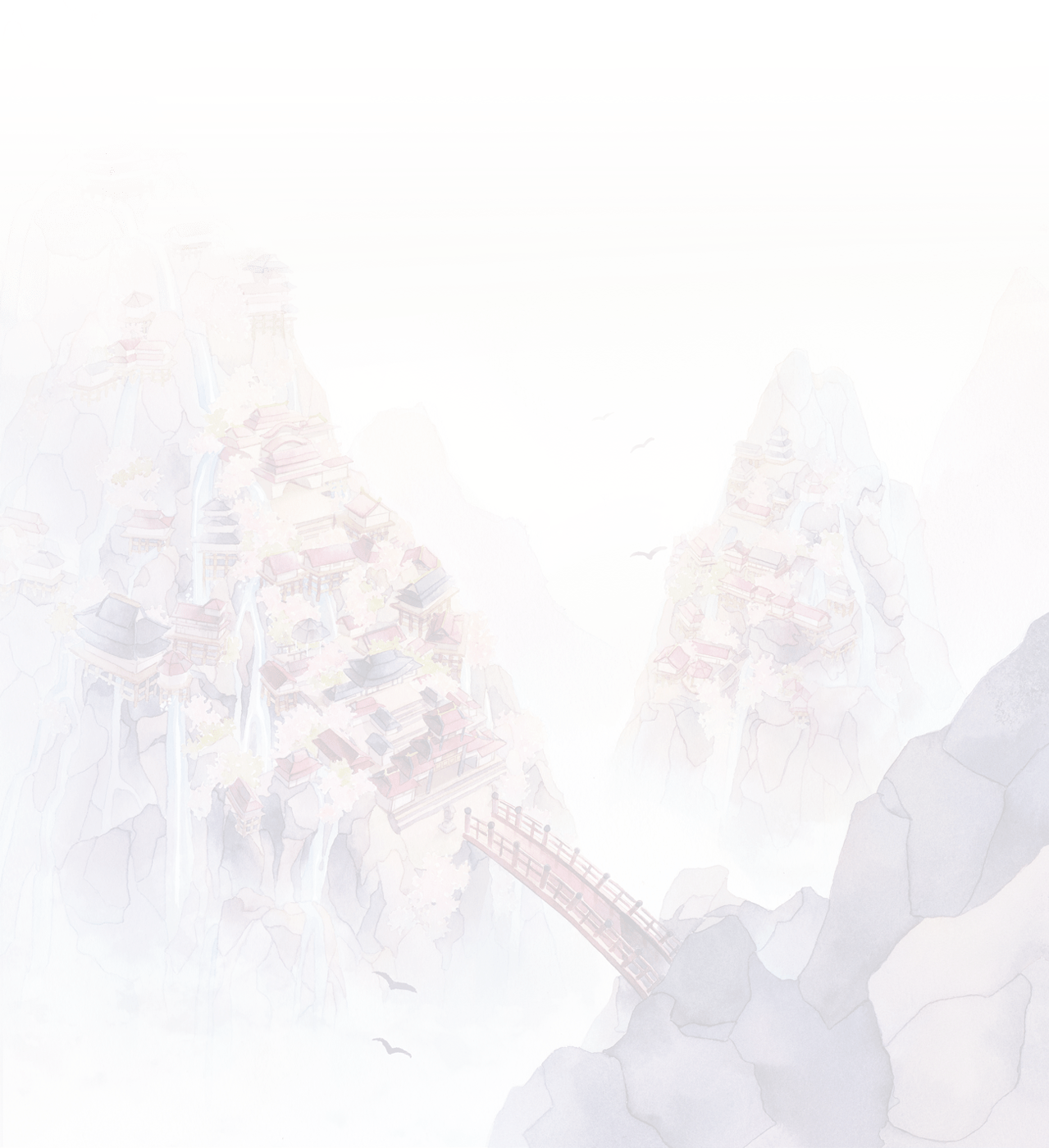

八咫烏シリーズは、二つの相反するコンセプトを持ってデザインしています。ひとつは、著者の中にすでにある、壮大で美しい、そして完璧なビジュアルイメージを、できるだけ忠実に多くの人に見せてあげたい、という使命感。もうひとつは、読者が自由に物語の世界を想像できるように、ビジュアルに柔軟な余白をもたせたい――この両立はなかなか難しいです。
デザインは、阿部さんと編集者、イラストレーターの名司生(なつき)さんと何度も話し合いながら進めています。他の本では、著者と直接やりとりすることは珍しいのですが、阿部さんは資料として手描きのイラストや切り絵を持参して、「異界感を出すため、この灯籠をほおずき型にしては」と提案されたり、逆に名司生さんのラフスケッチに刺激されて小説内の季節を変更したりと、共同作業ならではの面白さと、クリエイター同士の緊張感がありますね。
2020年夏からの文庫の新カバーは、6巻すべての装画をつなげることで、世界観の広がりや、絵巻物のように続いていく楽しさが表現されたと思います。次が読みたくてしかたなくなる八咫烏シリーズ、装丁を集めるためにも次巻をそろえたい、と思ってもらえたら嬉しいです。



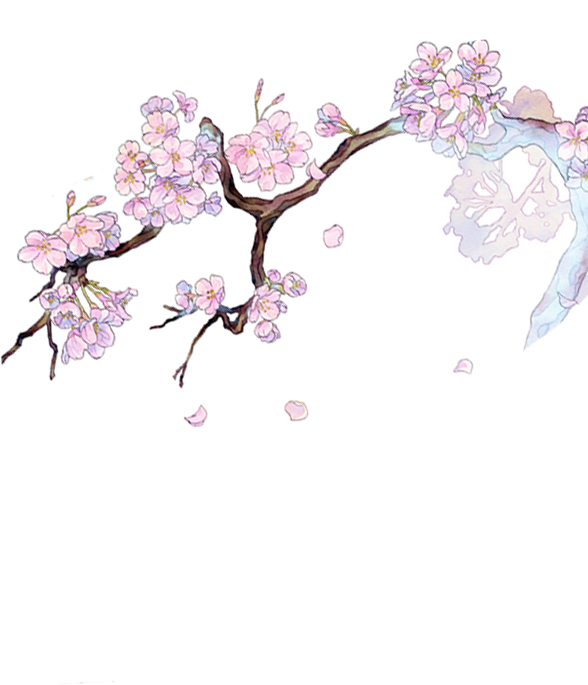


Twitter公式アカウント「八咫烏の壺」の“中の人”として、バズり具合に一喜一憂する毎日です。このアカウントの特色は、告知だけでなく、様々な企画を行っていること。読者から阿部さんへのQ&A企画は、好評につき「八咫烏シリーズファンブック」として電子書籍化されました。コミック版の連載開始前には、なんと著者による「登場人物へのインタビュー」を掲載。これは数ヶ月以上たった今も「いいね」が止まらないツイートです。
私はSNSをあるていど使い慣れている世代ですが、仕事となると「語彙力が足りない……」「これ誤報じゃないよね⁉」と一人でウジウジしてから投稿しています。「忘れてはいけない!」と予約投稿機能を活用したのに、それを忘れて、同じことを呟いてしまう失敗も。ツイート後はいつも動悸が早くなりますが、読者の反応がダイレクトに見えるのは楽しく、「もっと多くの方とつながって、作品を届けたい!」という想いが強くなります。
「八咫烏シリーズ」特設サイトも、さまざまな企画やインタビューをこまめに掲載して、何度も訪ねたくなるサイトを目指しています。
第1部完結後、書きおろしの新刊をお待たせしている間も更新をとめてはいけないと、日常をつづるコラム「作家の羽休み」をはじめました。隔週連載なので、締め切りのたびに「もう2週間…あっという間ですね…」と嘆きながらも、小説とはまた違う、ユーモアあふれる阿部さんの“素”が満載の原稿をいただいています!


熱烈なファンの多い「八咫烏シリーズ」。雑誌「オール讀物」に不定期で掲載される「八咫烏外伝」の短編を「単行本にまとまる前にいち早く読みたい!」という読者の声をキャッチし、電子書籍として1話ずつ刊行するという試みをはじめたところ、ほかの売れ筋に匹敵するダウンロード数になりました。いまでは一般的になった小説の「単話バラ売り」ですが、まだ珍しかったのです。
ほかにも、電子書籍書店とタッグを組んで八咫烏シリーズ特設サイトを作ったり、コミカライズ版とタッグを組んで無料試し読みコンテンツを作ったりと、さまざまな“実験”を行ってきました。電子書籍でしか読めない「八咫烏シリーズファンブック」「阿部智里BOOK」などオリジナルもあります。
ページ数や刊行スケジュールに制限のない電子書籍だからこそ、八咫烏シリーズの広大な世界観を、柔軟なスタイルでお伝えすることができるのです。




「八咫烏シリーズ」の漫画化オファーは10以上もありました。企画書と、候補の漫画家さんのプレゼン画を携えた各出版社の方と真剣な話し合いをし、著作権のプロであるライツビジネス部の知見も得ながら、最終的に阿部さんが選んだのは講談社「イブニング」。松崎夏未さんの作画で2018年に連載開始以来、編集部はもとより営業部も、講談社と文春でタッグを組んでいます。
2019年には前橋文学館で「阿部智里展」が開催され、私たちも企画パンフレット制作から展示物のキャプション監修に至るまで全面協力。「わざわざ足を運んでくださる読者に、前橋を楽しんでほしい!」という著者のアイデアから、急遽、市内のスタンプラリーを実施し、賞品のキャラクターうちわもつくりました。この時に文学館が制作したAR映像(来館者に烏の羽根が生える)は、その後、文春のプロモーション部による「AR雪哉といっしょ」(新刊の表紙をスマホアプリで撮影すると、主人公と一緒に写真が撮れます)につながりました。
出版社は、このように各部署が協力しながら、その作家だけが持つ魅惑の世界を正しく伝え、他業界の方ともうまく連携して、ファンを増やしていく役割を担っています。すそ野を広げていくことで、人気の頂点も高くなりますから。
その原点にあるのは、よりよい作品づくり。担当編集者チームは「阿部さんのイヤイヤ期」に伴走しています(笑)。いつもパワフルな阿部さんが、長編執筆の大詰めになると「この話、全然おもしろくないですよね……」とネガティブ発言を繰り返すのです。「見せたいものが伝わっているか」と考え詰めるあまり、食欲も落ち、どんよりオーラに……。創作者が突き当たるこの「イヤイヤ期」を、これからも全力で支えていきます!





個人として恩を感じている会社であると同時に、ビジネスパートナーとして最も信頼を寄せている会社です。
私が文藝春秋という会社を何より素晴らしいと感じているのは、作者と作品世界を尊重し、最大限守ろうとしてくれるところです。プロデビュー直後の私に、初めて顔合わせをした担当編集の方は「これから一緒に良い本をいっぱい作っていきましょうね」と言って下さいました。あれから約9年が経ちますが、あの言葉は、文藝春秋全体の文芸に対する姿勢だったのだな、としみじみ感じています。

今は出版社を介さなくても本が出せる時代、作品が発表出来る時代です。SNSなどでは編集者や出版社のマイナス面が強調されやすく、そういったものが不要であるという論さえ見受けられます。ですが、時代に即した形に変わることはあれど、創作者の伴走者としての存在価値は永遠に変わらないのではないでしょうか。
最初の読者でありながら「より良い本にしたい」という作者と同じ立場に立ってくれること。作者に代わって「本を売る」努力をしてくれること。
作家としての「阿部智里」を見つけ、守り、育てて頂けたのは、(人と人の関係が前提にあるのは言うまでもありませんが)出版社という大きな組織の力があったからだと感じています。
これをお読みになっている方の中には、きっと出版社に就職される方もいらっしゃるでしょう。その時は一緒に良い本をいっぱい作っていきましょうね!



